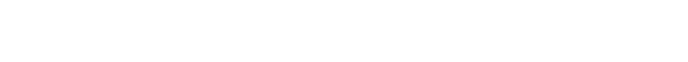echoes of "later" について
アルバム『later』の響きを五感で受け止めてくださった12名の方々が、テクストのかたちでエコー=木霊を返してくださいました。清冽であったり深遠であったり、あるいは時に滑稽であったり残酷であったり、さまざまな響きを湛えた木霊たちが声を交わしあう空間として、このページを公開します。制度としての「音楽」という軛から開放されて、それぞれの愉悦を生きる言葉の響き合いをお楽しみください。
秋山晃男からの手紙
※以下は、アルバム『later』に先行して私家版として制作された2曲入りシングルCD『Merei-traü / Performance studies 6』への感想として、編集者・秋山晃男氏からいただいた私信の抜粋である。転載をご快諾くださった秋山氏に心から感謝申し上げる。(福田貴成)
まず、ombrophone recordsの立ち上げと、その第1弾として久保田翠さんのCDアルバム『later』のリリースおめでとうございます。
CDのケースも滅多に見られないシックな意匠で、久保田さん、福田さんの今回立ち上げられたプロジェクトのコンセプトに、もう一つニュアンスが込められ、素晴らしいセンスに感心しました。チラシのコメントも含めて並々ならぬ意欲が込められていることが感じられます。それは久保田さん自身が書かれているように「長い時を経て、過去の自作が持っていた意味を、ようやく現在の自分が発見した」——その「発見」の大きさによるのですね。
久保田さんが「発見」されたことは、このいただいたCDの2曲と久保田さんのコメントだけで、私が、いや私だけでなく、ジョン・ケージ以来、色々な実験的なパフォーマンスを体験しながら考えてきた、なんとなくモヤモヤとしていた観念 (イデアと言ってもよいかもしれません) に、すっきり明快な答えを与えていただきました。
久保田さん自らの「演奏」で開いて私たちに示してくれた「発見」は非常に大きなことだと思います。それは重大であり、かつ意味は明快に示されているわけですから、このCDをこれから聴く方々も、おそらく“エウレカ!” と叫ぶにちがいありません。思いつきでオーバーな表現をしましたが、これはけっして誇張ではありません。音楽の次元だけでなく、私たちの生そのもの、生きていることの在り方の意味、誰かが言っていた言葉ですが、「意味のない意味」の美しい意味を具体的に開いてくれたからだと思います。
私は送っていただいた封筒が届いていた日、家に戻ったのが遅かったこともあって、寝室で封筒を開いて、まず久保田さんと福田さん自筆のお手紙入り挨拶文とチラシのコメントを拝見して、早く音を聴いてみたくて、いきなり挨拶文の下についていたQRコードにスマホをかざしたのでした。すぐに私の耳に、ワイヤレスヘッドフォンをとおしてMerei-Traüがきこえてきました。美しい音です。イヤホンで聴くので夜に相応しくとても静かで落ち着いた響きです。これまで聴いたことがあるようでない不思議な響き。ときどき特殊な楽譜の読み方から起こるらしい、からだの反応と息づかいもきこえてきます。しかし音楽は脈絡がないようで不自然さはまったくなく、響きそのものが美しいのです。
2曲目のおそらくバロック期の対位法作品にもとづくPerformance studies 6も、響きのニュアンスは違って別の味わいを生み、私はそこに自然に身を任せてきき入っていたので、演奏がふっと途切れたとき、なんだか惜しむ感じがしたくらいです。
これはどういうことなのだろう。私が無心に聴こうとしている、というより,無心にきこえてくる、と言ったほうがよいでしょう。インストラクションに従って通常でない楽譜の読かたで弾く弾き手にとっては難しい作業にちがいありませんが、一生懸命リアライズしようと集中する身体は、無心そのものであるでしょう。そこから立ち上がる響きを私(たち)はきいているのです。インストラクションは作為に基づくともいえますが、結果は作為を超越している。その響きの中に、久保田さんが「発見」したすべての意味が込められている、ということですね。私はそんなふうに理解しました。
これまであたりまえに慣習として読んできた伝統的楽譜を、例えば楽譜を逆さまにして読む、と言うようなやり方はこれまでもありましたが、それは殆ど反伝統主義といったダダ的な感覚にとどまっていたように思います。久保田さんの方法はそれとは違って、インストラクションを用意し、身体的には敢えて困難な譜読みを強いる。読み違っても、弾き違っても、躓いても、すっ飛ばしても、瞬間瞬間をそのまま受け入れ演奏を続けなければならない。そこに思わぬ偶然、思ってもみなかった響きが生じる。与えられた枠にある意味で閉じこめられながら、それに抗して、その瞬間瞬間を受け止め、受け入れるなかで、偶然、美しい出会いが生まれる。これはまさに「生きていること」の隠喩とも言えます。
しかし、これはケージの偶然とはだいぶちがっていますね。
アンビエント音楽のように気持ちよくきこえる音楽の背後に、実は極限に近いような困難をも伴うインストラクションの枠が設定されているからです。そのことはこのC Dに付されたブックレットに久保田さんご自身が書かれている「疲労について」という文章を読まなければ、私はこのプロジェクトの本当の意味は分からなかったでしょう。この文はこの困難な演奏過程の一見ドキュメンタリーのようなかたちで書かれていますが、しかしこれらの言葉は演奏の即物的な次元の語りを超えて大きな意味を暗示しています。
この最後の段落の最後は、このように止められている。
「——「自分の音」と「自分のものでない音」は危ういバランスで互いに連なりあい、不思議な響きを導き出す。だが弾いている間の私は、それを聞くことが出来ない。なぜならば目の前のタスクをこなすことで精一杯で、「音の連なり方」まで聞く余裕はないからだ。瞬間ごとに判断し、瞬間ごとに忘れてゆく。その結果を、私はのちに(later)録音を聴くことによって、知ることになるのである。」
私は読み終わって、このプロジェクト全体の意味を一挙に理解しました。このパフォーマンスはまさに「生きていること」の隠喩とも言えます。与えられた枠にある意味で閉じこめられながら、それに抗して、その瞬間瞬間を受け止め、受け入れるなかで、偶然、美しい出会いが生じる。
久保田さんは「音楽作品というより、音楽行為のドキュメンタリーではないか、と思った」、あるいは「行為の影としての音楽がまとうあらたな相貌」というように語られていますが、私はこのパフォーマンスのすべては、人間の生そのもの、生きていること、企てること、行為すること、そこに常に伴う偶然、そして音楽自体の美しい沈黙、それを私は「生」そのものメタファーであると読みました。
福田さんはombrophone recordsを立ち上げるにあたって「音の影/影の音」「影の言葉を話す人」というような意味を込めてこの名前を選んだと言われています。そして「声高で直接的な表現からは限りなく距離をとりながら、静けさや弱さ、そして間接性の中にこそ宿る表現の勁さ」を模索するプラットフォームとすると述べられています。
これらの素晴らしい言葉の目指す究極はまさに「沈黙」ですが、この第1弾、久保田翠さんの『later』のコンセプトと美しい響きは、まさにこれらの言葉に呼応している、と私は思いました。
秋山晃男(あきやま・てるお)
(株)アルク出版企画代表取締役。編集者、プロデューサー。慶応大学で仏文学を学ぶ。松平頼暁氏に作曲を師事。主な仕事として『音楽の手帖』シリーズ、小泉文夫著作集、柴田南雄、高橋悠治、間宮芳生、湯浅譲二、八村義夫などの音楽論集、『ジョン・ケージ 小鳥たちのために』(以上、青土社刊)。坂本龍一+高橋悠治『長電話』(冬樹社)、武満徹『夢と数 音楽の語法』(リブロポート)、『堤清二/辻井喬 フィールドノート』(文藝春秋)、『小泉文夫と世界の民族音楽展』(西武百貨店)、『世紀末ウイーン展』(セゾン美術館開館記念)、武満徹の企画構成による『MUSIC TODAY』、『八ヶ岳高原音楽祭』のアシスタント、雑誌『MUSIC TODAY Quarterly』編集長。また、安芸光男のペンネームで音楽批評、エッセイなどを執筆、著書に『クラシックの名曲101』(新書館)、 ロングインタビュー『武満徹自らを語る』(青土社)など。
『later』をはじめとする久保田翠さんの音楽を聴いているとどこにいてもそこはここちよい室内になる。そこではバッハの絶妙な残響が響きあっている。それだけではない。聴きつづけていくと、その音楽はまったく新しい音の連なりとなってあらわれる。わたしたちはその静かな美しさと官能性にいつまでも包まれていく。
朝吹亮二(あさぶき・りょうじ)
1952年生。詩人、フランス文学。詩集に『朝吹亮二詩集』(現代詩文庫)、『まばゆいばかりの』、『ホロウボディ』(いずれも思潮社)。
シネマティック・ピアノの誕生
荒川徹
今回、『later』を発表した久保田翠さんから、私がGoldmundの『Two Point Discrimination』について書いていた「マテリアル——情動のタイムドメイン」(『Review House 02』)という2008年の批評を読み、影響を受けたという嬉しい言葉をいただいた。今回の機会に、当時は記せなかった、12年後の補遺を記しておきたい。
Goldmundのキース・ケニフは、『ドニー・ダーコ』(2001)の音楽を手掛けたマイケル・アンドリューズから、ピアノのミュート使いに大きな影響を受けたと語っていた。Goldmundは、『Corduroy Road』(2005)とともに、「オンマイク」、つまりマイクをピアノの発音機構に近づけた録音、そして、モートン・フェルドマンにも影響を受けたというスローモーション的な動きによって、ピアノの楽音そのものより、それにまとわりつくピアノの発音機構や無数のノイズが意識される音楽を生み出した。ミニアルバム『Two Point Discrimination』(2007)では、プリペアド・ピアノの物質的トーンによるミニマリズム的反復が行われ、その実験性は極点に達する。
しかし、Goldmundはそれ以降、ローファイ加工のノスタルジック路線にシフトし、シンセサイザーを多用したニューエイジ的展開を強め、現代音楽・実験音楽の要素は消滅することになる。商業的な方向づけもあるだろう。コンポーザーとしてGAFAつまりApple やFacebookのCMを手掛けることになるキースは、レコーディング・アーティストというより、クライアントワークの音楽に傾斜していくからだ。Goldmundのピアノトーンにあった実験的可能性は、2000年代後半のポストクラシカル・シーンという時間に凍結されたままである。
Goldmundのピアノ音を、「シネマティック・ピアノ」と呼んでおこう。それは、フィルム撮影を模して24fps、オールドレンズ風のボケ味の多い映像で撮られたシネマティックなヴィデオ映像の音楽版ともいえるものだ。映像制作者のためのライセンス音楽サイトArtlistに登録されているピアノの音楽は、フィリップ・グラス似で音はGoldmund調のようなものばかりであり、「シネマティック cinematic」というタグがその使用法を集約しているだろう。オンマイクの可能性は、レトロ加工として映像音響産業のなかに過剰消費されてしまったともいえる。
だが、Goldmundは別として、それ以降も、ピアノトーンを物質化する試みはさまざまに行われた。現在までのポストクラシカルの動向を中心とした、ピアノの物質化の諸局面をみてみよう。
1. アップライトピアノ
Goldmundと当時同様にオンマイクのピアノ音にこだわっていたのは、チリー・ゴンザレス(最近エンヤ論を出版した)がゴンザレス名義時代に発表した、2004年の『Solo Piano』である。ゴンザレスはその後、楽曲の緻密さを高めつつ(フランス印象派を簡素化したという意味で坂本龍一に近づきつつ)、『Solo Piano III』まで生み出した。ゴンザレスはベヒシュタイン製のアップライトピアノをスタジオで用いる。アップライトは、音の高低を問わない均質性という観点では、残響の長さなどに明らかな不完全さが出るが、むしろ完璧でないことによって、物質的過程として不透明な、ピアノという媒体それ自体を聞くのには適している。
アップライトという点では、山田尚子監督の映画『聲の形』の牛尾憲輔による音楽は、実家のアップライトピアノという音素材を生かし、ピアノ内部にマイクを突っ込んで録音したものを加工している。視覚的にも色収差(レンズにより視野の周縁で色ズレが生じる)を強調した設計と重なり合い、聴覚障害とそのディスコミュニケーションを描いた物語に、骨導音的な質感を与えている。
2. プリペアド・ディスクラヴィア
『ドニー・ダーコ』と同時期で大きな影響力があったのが、プリペアド・ピアノを用いたエイフェックス・ツイン『Drukqs』(2001)である。オープニングは、サンプリングサウンドではなく、生音で録音されたプリペアド・ピアノを用いていることで、当時のリスナーに驚きを与えた。私も例外ではないのだが、多くのリスナーはリチャードがピアノを弾いていると思っただろう。しかし、実際はヤマハのディスクラヴィアによる自動演奏だった。リチャードは、ピエール・バスティアンの機械音楽に大きく影響を受けたようだ。
そこから長く経ったのち、その試みの第二弾となる、『Computer Controlled Acoustic Instruments pt. 2』(2015)が発表されたが、もし彼がセレブではなかったら、このようにきわめて断片的な実験音楽が大体的にリリースできたかどうかは怪しい。明らかにYMOの「Neue Tanz」におけるガムランを模したプリペアド・ピアノに影響を受けたトラックも見られる(蛇足だが、同じYMOの『テクノデリック』の「Stairs」では、劣化音質サンプルの異様に卓越したピアノ・ソロを聞くことができる)が、ここでは「DISKREPT1」というメカニカルな曲に注目してみよう。どうやら遠くでリチャードの息子と見られる子供が喋っているのがわずかに聞き取れる。密閉されたスタジオ録音ならあまり起こらないことであり、自宅のオープンな環境を感じさせる。
そもそもエイフェックス・ツインのプリペアド・ピアノは、ジョン・ケージのピアノ音楽との共通点も多いが、ケージであれば、日本でも「キノコ盤」と呼ばれて愛されていたCrampsのレコード『John Cage』(1974、サブスクリプション化されている)の冒頭、フアン・ヒダルゴ演奏による「マルセル・デュシャンのための音楽」を大きな音で聞くと、オンマイクでピアノの内部共鳴を拾っていることが分かる。水中のような空間を感じる。映像のカメラワークが現在も無限に開拓されているように、ピアノの録音も、マイクワークの可能性があるはずなのだ。
3. 巨大ピアノ
物質化の方向として、ピアノの巨大化という方法もある。ニルス・フラームの『SOLO』(2015)は、使用しているピアノが特殊すぎる。Klavins M370というその巨大なピアノは、チュービンゲンに位置する2階建てのもので、パイプオルガン級のスケールを有する。低音弦は、まるで吊橋のワイアーのように極端に長い。Klavinsによるレコーディングは、Thomas Duisというピアニストがクラシック曲で行っており、長岡鉄男にも評価されたようだが、恐縮ながら私は未聴である。
ポストクラシカルは、たとえば坂本龍一などの先行する例と比しても、楽曲構造が単純すぎ、エモーショナルだが古典的な構成の精度を満たしていないものが多い(シネマティックな「エモ」に流されているといえる)。一方で、機構音や空間系エフェクトを含む音色の豊かさは、歴史的にも例をみない。ニルス・フラームの音楽はその最たるものだ。「Some」という曲は、野心的ではない定番のコード進行を、ハンマーアクション音とともに、ひたすらゆっくりとエモーショナルに繰り返すだけだ。だが、これほどにKlavinsのスケールに見合った音楽があるだろうか。高音部のフレージングは、残響の多さとともに、レトロ加工されたシンセサイザー音にほとんど近づいている。低音成分の豊かさは、物質的なイコライザーになっている。そこには、クリストファー・ノーランがCGを避けて実物で視覚効果に取り組むのと同様の物質重視をみることもできる。
シネマティックとはまさに、シネマスコープのようなアスペクトのスケール感、粒子ノイズ、光学的歪みなどからなる総体だが、ポストクラシカル以降の音楽において録音方法が問題となるのであれば、われわれはもっと映像技術と音響技術を同じ方法論で思考する必要があるのだろう。『later』は、選び取られた楽曲の喚起する強いノスタルジアもあり、まさにシネマティックと言えるが、その美しさ自体を考えるための時間が内包されていると思う。
荒川徹(あらかわ・とおる)
1984年生。視聴覚芸術研究。現在、日本学術振興会特別研究員。著作に『ドナルド・ジャッド 風景とミニマリズム』(水声社、2019年、吉田秀和賞受賞)がある。最近の論考に「マイクロレイヤーズ 戸田ツトムとタルコフスキー」『ユリイカ 2021年1月臨時増刊号 総特集=戸田ツトム -1951-2020-』(2020年1月号)など。
このCDの非常に想像的な音楽の中に、私はクラシック音楽の微かな痕跡を聴きました。クラシック音楽それ自体ではなく、クラシックピアノを長年演奏したのちの夢の記憶のようなものとして、です。
久保田翠は、親しさと革新を結びつけることによって、伝統的な音楽に創造性を持ち込む方法を発見しました。彼女の音楽は、ピアノの歴史とピアノによって演奏される音楽に共鳴します。
音の順番が変わる時、複数の協和音は混じり合い、独自の音風景を形作ります。サウンドは微かに親しみ深いものですが、時たま不協和音とともにあります。聴いていると、全音と半音の調律がピアノの全ての音域に共通であるということを思い起こさせます。つまり、振動数の算術が楽器を統一し、世界中のほぼすべての文化における音楽へと結びつくのです。
Listening to the highly imaginative music on this CD, I heard whisps of classical music while not hearing the music itself, like dream-memories after years of playing classical piano.
Midori Kubota has found a way to bring her creativity to traditional music, combining familiarity and innovation. Her music resonates with the history of the piano and the music played on it.
Harmonies mix to form original soundscapes when the note orders are changed. The sound is vaguely familiar, with occasional dissonance. Listening reminds me that the tuning of whole tones and half tones is common to every register of the piano: the arithmetic of frequency unifies the instrumentand connects with music from almost every culture in the world.
ゲイル・ヤング(Gayle Young)
カナダの作曲家・パフォーマー。作品のみならず、アマランスという楽器の発明や、Musicworks magazineのエディターとしても知られている。
歩くのがおそい
河野聡子
一方通行の出口にある横断歩道では、いつも長い時間待たなければならない。
歩行者用信号が青になっても、向かい側の道路から右折してくる自動車は、わたしが道ばたにいようといまいと横断歩道を横切っていく。
わたしは自動車が通りすぎるまで足をとめて待つ。
自動車がわたしにぶつかってきたら、自動車は生きてもわたしは死ぬかもしれない。
わたしはまだ死にたくない。
だから待つ。
自動車の中の人にとってこれが法律的に正しい行為なのか。
待っているあいだ、いつも不思議に思う。
サバンナの獣は自動車をそれぞれ独立した生きた個体だと認識しているときいた。
だからサバンナの獣は、自動車の中の人が車を下りると、生きものから内臓が飛び出してきたと思い、驚いて襲いかかってくる、というのだ。
ほんとうにサバンナの獣たちがそう思っているのかどうか、わたしは知らない。
しかし路上を歩く人間にとって、今まさに動いている自動車が、ゾウやライオンやシマウマとおなじようなものだということには、わたしも同意する。
ヒトはかよわい生き物だ。
自分より大きくて素早い速度で移動する獣にぶつかれば、死んでしまうこともある。
そんなことをわたしは自動車が去るのを待ちながら考えている。
横断歩道の信号が点滅しかけた頃になってやっと、道をわたることができる。
わたしが道をわたりおえるころ信号は赤に変わりかけている。
わたしは歩くのがおそい。
それでも完全に赤になった時には、横断歩道の先のゆるい下り坂を歩いている。
マンションの前を一軒通りすぎるとすぐ、左へ曲がる道がある。
曲がった道の先は一見行き止まりのようにみえる。
実際は、行き止まりの先にある、舗装されていない土と石の階段をのぼれば、ちいさな社の裏手に出る。
社も道も誰かの所有物にちがいないが、わたしは二回ほど通ったことがある。
その時はまるで猫になったような気分で、すこしどきどきした記憶がある。
まっすぐ歩くと、左側に金木犀の生垣がつづく。
数か月前に金木犀が咲いていたと覚えているので金木犀だとわかるのだ。
春になったらもう忘れているかもしれない。
金木犀は、植物にほどほどの興味しかもたない人間が、匂いだけで認識できる数少ない草木のひとつだ。
わたしが花の香りだけで認識できる草木は金木犀の他にもある。
しかし数えるのは片手で足りる。
梔子、沈丁花、ジャスミン、これで完了である。
花の香りはだいたい遅れてやってくる。
匂いは空気を介し、風に乗ってわたしの感覚に届く。
わたしはいつも匂いの風下にいるとはかぎらない。
わたしがいま歩いている道路は、通行量のわりに不自然に道幅が広い。
そして、その広さのわりに短い。
歩くたびにいつもそう認識する。
路線バスがゆったり通れそうなくらい広く、バス停にちょうど良さそうな車寄せもある。
それでもバスが通ったことはない。
わたしの右手、南側には、五階建てのマンションや二階建てのアパートがある。
道幅が広いから、建物の影は道を覆わない。
この道を歩くときは、雨が降っていても曇っていても、世界をより明るく感じる。
わたしの左手にたくさんの草花が咲く家がある。
家はいま、南側から照らす太陽の光を受けている。
タイルを貼った塀に、鉢植えとプランターが隙間なく掛けられている。
この家では一年中何かしらの花が咲き、いまはパンジーが大きな目のように花びらをこちらに向けている。
パンジーのプランターを通りすぎて、広い道は終わる。
わたしの前には小さなトンネルが待っている。
これは上に線路を通すためのトンネルだ。
このトンネルの幅の95パーセントは自動車のためにある。
歩行者が通れるスペースは40センチほどしかない。
だからわたしは向こうからくる自転車や、ベビーカートを押す人をしばらく待つ。
上の線路を通る電車は音に遅れてやってくる。
わたしが待っているあいだに頭上の線路に音が響き、つぎに電車が通り抜ける。
わたしはトンネルをくぐる。
トンネルのむこうには、線路沿いの道と、大きな通りへつながる広い道と、アパートと家に挟まれた狭い道がのびている。
わたしは狭い道をえらぶ。
この道には日が当たる部分と、当たらない部分がある。
いま太陽はわたしの右手、南の方向にのぼっている。
わたしの左手に建つ家の壁沿いの植え込みが照らされている。
花は咲いていないが、この植物がラベンダーだとわたしは知っている。
ラベンダーは葉のかたちでみわけることができる植物のひとつだ。
わたしはラベンダーの家を通りすぎる。
唐突に、巨大なケイトウが出現する。
ケイトウとは、太さ2センチ、高さ1メートル以上はある、一本の草だ。
誰かの家の敷地ではなく、あきらかに、舗装された道路の上に生えている。
南側から降り注ぐ太陽の光で、先端の鮮やかな赤が輝いている。
どうしてこんなことが許されるのだろうか。
わたしは驚き、立ち止まる。
認識はいつも遅れてやってくる。
わたしの頭に、風に吹かれて飛んできた小さな種のイメージがうかぶ。
ひとつではなく、たくさんの種だ。
道路の上におち、舗装の隙間から根をのばすことのできた数本から芽がのびる。
そのうちのいくつかは、太陽があたらない場所に生えて、やがて枯れる。
べつのいくつかは、雨に流されて、やがて消える。
残った一本が、犬や人の足や自転車、自動車のタイヤに踏みにじられることなく上に伸び、太くなる。
そしてこのケイトウに育つのだ。
納得しましたか?
はい。
わたしはまた歩きはじめる。
右側にフェンス、左側に壁があらわれる。
フェンスのむこうは保育園で、フェンスに沿って樹木がまばらに植えられている。
フェンスからはところどころに木蔦が垂れさがっている。
壁の上には家が建っている。
道はますます狭くなり、ゆったりとしたS字を描いている。
中央に排水溝の蓋が嵌り、これもゆるやかにS字を描いている。
昔ここには小川が流れていたにちがいない。
南側から、保育園の建物と樹木をこえて、太陽の日差しが斜めにおちている。
太陽に照らされているのは、わたしの左手、左側の壁だ。
光に沿って、カラスノエンドウや、わたしのしらない草がびっしりと生えている。
舗道の割れ目に根をおろし、半分茶色く刈れている。
明るい日なたを通っていくと、急に樹木の影がまるく落ちる。
わたしは上をみあげる。
深緑の葉のあいだに黄色い実がぶらさがる。
柑橘の木だ。
壁の上に建つ家の塀の向こうから、枝を外へ、道の上へと伸ばしている。
黄色い実には、誰も手が届きそうにない。
樹の枝はわたしの頭上で大きな緑の手のひらのように広がっている。
太陽を受ける手のひら。
堅い緑の葉をつけた木のからだが、降る光を受けとめている。
わたしは柑橘の影を通りすぎ、道のおわりに到達する。
日なたの痕跡を追うものは、いつも遅れてやってくる。
河野聡子(こうの・さとこ)
詩人、書評家。ヴァーバル・アート・ユニットTOLTA代表。刊行詩集に『時計一族』(思潮社)『やねとふね』(マイナビ出版)『地上で起きた出来事はぜんぶここからみている』(いぬのせなか座)ほか。書評や論考、エッセイを文芸誌、新聞等に寄稿。実験音楽のユニット「実験音楽とシアターのためのアンサンブル」メンバー。
久保田翠 later
小沼純一
知らないところでひびいていたとして、それはそれ、ここちよさとちょっとした違和感のまじりあった楽曲――なのだろうと感じるはず、か。ちょっとした違和感があるのか、違和感がどこにあるのか、違和感が気になるかならないか。
久保田翠のアルバム『later』、全11トラック。それぞれ曲名らしきものはついているが、さしたる特徴はなく、Performance studiesとの抽象的な呼称は、ひびいているものの何か――何か、とは何か? 内実? まさか――を知らせるわけでもない。
気になることをすこしはこまかくみられるだろうか。じぶんのなかにあるものに分けいってみられようか。
知らないひびきなのに、ほんとうに知らないかとみずからに問いたくなってくるような、もしかしたらどこかで耳にしていた、知っていたという既視感・既聴感、いや、既聞感があるようなないような。あるなつかしささえ、ある。それでいて、ここちよいでなく、ふつうの楽曲のようなのに、おもいがけない不協和がおこり、「楽曲」「音楽」がふつうにおりなしてゆくときのながれがねじれている。ねじれている感が、ある。
トラックをすすめていくうちに、わかるもの、うきあがってくるもの。ここにあるのは、バッハだ、と、高名な変奏曲だ、と。あるいは、ピアノの残響、ペダルで上下するダンパーのかるい衝撃、トイピアノの金属音、女声のうごき、どこか空気の密度を意識させるような。
- 2017年1月6日および2019年6月22日・23日にかけて、私の作品のいくつかが演奏された。
- 本CDに収められた音源は、そのドキュメンタリーである。
- “Performance studies”はインストラクションのみから成り立つパフォーマンス作品のシリーズである。
- 奏者は任意の既存曲の楽譜を選び、それぞれのインストラクションに合わせて、演奏を行う。
- 選んだ楽譜をすべて演奏しきった時、作品は終了となる。
ジャケットの裏側に、また、ブックレットと呼ぶべきかライナーノートと呼ぶべきかわからない、内側にある印刷にも同様に、こう記されている。
各曲、インストラクションが黒い文字でおよそ中央、薄墨色の文字でべつの、もすこし思索的な断片(アフォリスム?)が右下に記されて。どちらにも英語もあって。例外はアルバム・タイトルにもなっている《later》、これだけはインストラクションがない。また、《Poem 詩》は谷川俊太郎の詩を引いて。
《Performance studies 1》をみてみる。
- Instruction:
- 任意の楽譜を選びなさい。
- 骰子をふり、1~5までの数字をひとつひとつの音に書き込みなさい。
- その数字を指番号として演奏しなさい。
- 私たちは、あるいは私たちの耳は、つねに音へと遅れている。
- 世界はいつも遅れてやってくる。音は私の影となる。
ことばがあるだけでなく、CDアルバムというほぼ正方形のどこに、どんなふうに文字を配置するかと、レイアウトも考えられて。だから、英訳をぬかし、色も変えず、タテガキにして、という引用では伝わるものも伝わらないかもしれない。それはご容赦願うしかあるまい、とりあえずインストラクションの「意味」、「指示」と、アフォリスムのありようだけでも読んでいただけばいいとしよう。
インストラクションをみると、どうしても一九六〇年代のフルクサスでおこなわれたパフォーマンスや、シュトックハウゼン《七つの日より》といったものを想いだす。でもきっとこれは余計。ここにあるのはもっと(楽器=道具にたいして)具体的。ヘンに文学的なレトリックや「直観」は排除され。演奏しようとするなら、いきなり、ではなく、あらかじめ「楽譜」を「選」び、「数字を書き込む」必要があり、「演奏」には、練習もしなくてはならない。
やっておかなくてはならないプロセスで、演奏者が試行・思考し、指をうごかし、音に耳をかたむけるなか、また何かしら気づくことがあり、考えることがある、あるはずだ。そうしたことを含めてのインストラクション。ステージなりどこかなりで演奏され、ひとが臨席して耳にいれる「事態・出来事」はここで欠けてはいるのだが、その空間的・時間的へだたりも、ここ(ジャケット内)には余白(そのもの)に記されている。そうおもってみるなら、黒い文字で記されたインストラクションと薄墨色のアフォリスムのコントラストは、アルバムに録音された演奏、演奏が再生されることとはべつになりたつ空間・時間のようでもある。音源とはべつになりたつアルバムなるものの造形的・言語的なオブジェ。
ひとつひとつのインストラクションをみていく――と、「楽譜を上下逆にし、そのまま通常の読譜をして演奏」(2a)したり、「再下声部のみ1小節遅れて演奏」(5)したりと、それなりの手間がわかる。楽譜があれば、それをさまざまなかたちで演奏できるというならともかく、与えられたものをただ弾くだけに慣れているなら、ひとによってはわざわざべつの楽譜に書きうつして練習しなければならないし、ときにあたまの混乱も避けられない(かもしれない)。まあ、そんなひとはあえてやってみようとなどしないかもしれないが。
インストラクションのある「Performance studies」をひとつだけ抜きだし、独立したものとして扱うのでなく、いくつものインストラクションをセットにし、文字どおりこのアルバムでのように、ひとつのながれにするときには、ひとつだけ単独に、とは違った思考・志向性が必要になる。これはプログラミング力、構成力と言い換えてもいいし、アルバムやコンサートを「コンポジション」する力と言い換えてもいい。ひとつひとつの既存曲の選択はどうするか、全体はどうするか、どうなるのか。個々の楽曲は個々でのみあるのか、それとも全体としてあるのか。久保田翠がCDアルバムとしてリリースしたのは、おそらく、こうしたことを、ネット配信でランダムに聴かれるのとはべつの、こうしたならび、こうした順序、構成になっていることを、提示せんとしたところによる。
インストラクションは、演奏家が(そのまま楽器を)演奏する――この場合はピアノを想定――のが前提。でも、もしかすると、「任意の楽曲」を、既存のパート録音やパート譜での演奏を、あらたに組みあわせるやり方も可能かもしれない(テープ・コンポジション、との呼称もかつてはあった、ような)。ヘンな言いかただし、ピントがずれているかもしれないが、DJ的な、リミックス的なテクニックとも(直接ではないかもしれないが)つながっているだろう。久保田翠の試みは、既存曲をもとに、というところからみても、サンプリングやリミックスと連続する。つまりは、すぐれて二十世紀末から二一世紀の音楽のありかたとおなじパラダイムにあり、しかも楽譜を書く「作曲」の、楽譜を読む「演奏」の、別解としてある。
アルバム『later』を何度もきいた。わざと、ねむりにおちるようなときにながしておくこともした。なにか夢をみているような気もした。夢、よいものか、わるいものか、それもおぼえていない。(良/悪)夢? さして意味はない。夢がよい・わるいでなく、なにかしら夢そのものがちょっとだけ奇妙なものだった。それは記憶している。夢だからありうるような、か。夢は――ねむってからみるものなのか、ねむるまえからみているものなのか……まだ覚醒しているときにおもっていることがそのまま夢にはいりこんでしまう、しみこんでしまう、つづいてしまうことがあって、『later』ではほかのものがながれている、耳にはいってくるよりも、「しぜん」であるような……。音に、音楽に、ひとが遅れ、つねに遅れながら、かたちをとらえる、とらえようとしていることと、ひびきあうのかあわないのか。わたしにはまだわからないのだけれど。
わかる?
わかるようになる?
あとで? later?
小沼純一
1959年生。音楽文化論研究、音楽・文芸批評、など。著書に『武満徹逍遥』、『ふりかえる日、日』(ともに青土社)ほか。
『later』に潜む、アカルイミライ
佐藤良明
『later』には、「パフォーマンス・スタディーズ」と呼ばれる一連の演奏実践が収録されている。ある出来合いのメロディを、楽譜をひっくり返したり小節を逆向きに演奏したりして虐待する。あるいは鍵盤に触れる指を不自然に変えさせて演奏者を虐待する。結果どうなるか——というと、あまり悲痛な感じもしないのだ。うわべは冷静。繊細な指のふるまいは崩れない。突然、蹴るようなスフォルツァンドが入っても、音楽自体の上品さは動じない。
「任意の大譜表の楽譜を選びなさい……」。指示のことばは無慈悲だ。「下の段は普通に、左から順々に弾いていきなさい。と同時に、上の段を右の小節から始めて順に左へ弾いていきなさい」。いわれなき指示に、奏者は抗わない。「すべての鳴り響いた音は、それぞれがひとつの出来事」なのだと、ふがいなさを振り払い、出来事としての自己のドキュメンタリーに向かい合う。
いっけん冷静なサウンドに、どんな出来事が包まれているのか、僕らも想像せざるをえない。『later』を聴くのは、ショパンを聴くのとは訳が違うのだ。「子犬のワルツ」を聴く聴衆は、その軽々とスピーディな運指による音の転がりに魅せられ、「芸術」を繰り広げるための努力の少なさ(effortlessness)を祝福する。久保田翠が試みるのは、それとはまるで逆向きのことだ。最大限の努力をしても、おさらい会に登場したできの悪い子のように途中で立ち止まってしまうピアニストになろうとする。「長年かけて覚えこんだ楽譜への反応の仕方は改変するよう迫られ、事前に備えることのできない数々の問いに、その都度応えていかねばならない」(「疲労について」より)、そんな不条理な状況へ自らを追い込もうとする。
作品を美しく奏でるべく調律された身体をどうして羽交い締めにするのか? これは後ろ向きで自転車を漕ぐのにも似たピアニストの曲芸なのか? そうではない。このパフォーマーは見せびらかさない。逆境に抗ってやり遂げるのではなく、ちゃんとできないことを誠実に示そうとする。なぜなら、できないことがポイントだから。演奏されるべく演奏してしまう凡庸な音楽家でなくなること。身についたスキルを攪拌し、既成の「調律された自分」から自分を引き剥がすこと。その浮遊の中に一回起的な生の充実を感じること。そのために、久保田は、謙虚に、ひとり、ピアニストとしての身体を虐めながら、GarageBand ならわけもなくやってくれる変換に挑んでは不面目な成果をドキュメントしつづけるのだ。
そのマゾヒスティックな欲望はなんだろう。何に対して、彼女はたたかっているのだろう。
「芸術の過飽和」という事態を考えてみる。芸術の欠乏を背景に、芸術家が社会的エリートして機能しえた時代は去った。芸術を生み出す欲望はすっかり大衆化し、それが教育インダストリーを活性化し、ソフトウェアの開発と相まって、それなりの「見事さ」をインターネット上に溢れさせ、かつてならそれぞれ「芸術」として切り出しえたものを、単にそこそこアートっぽいシミュラクルに変えてしまった。
才能に恵まれた子が、理想的な指導を受けて研鑽を重ね、東京芸術大学音楽学部に入学し、無事卒業証書を手にしたとする。高度な技術、頼れる音感、権威による認定、すべてを得たその子は、実際のところ、現代に響きわたる何を得たことになるのだろう?
2001年秋、学部卒業を前にした久保田が、東大駒場の表象文化論コースを進学先に選んだのは、もしかしたら学科の中心にいたひとりが、芸術と凡庸さの関係について切り込んだ論を展開していた思想家だったことと関係するのかもしれない。
蓮實重彦の凡庸論の非凡さは、「凡庸さ」を超克する才人たちの営みに「愚鈍」を見いだすところにあった。芸術の前衛をナイーブに信じるミーハーたちにこの見解は堪えた。デュシャーンの「泉」にせよ、ジョン・ケージの「4’ 33”」にせよ、それ自体を見れば、「何をやってるんだよ、バカだなあ」と笑わざるをえないような、愚かしい行為であることに、みんな気づいていないわけではなかったのだ。
自分が大学院に入った頃はどうだったろう。70年代なかば、「ポストモダン」ということばが流行りだして、かつてアヴァンギャルドと呼ばれ、なんだか壮絶で難解な感じがしたものをお手軽に楽しめる雰囲気が広がった。僕が愛したポストモダン・フィクションの中に、たとえば Alphabetical Africa (1974)というのがある。わざと不自由に物語を綴るその愚かしさのスタイルが、久保田の『later』とも通じるところがある作品だ。著者ウォルター・アビッシュはここで、各章の使用単語をその頭文字で規制することに挑んでいる。最初の章はAで始まる単語しか使えない。 Ages ago, Alex, Allen and Alva arrived at Antibes, and . . .で始まる物語が2ページに及んで、男3人と女1人が、南仏 Antibesを出帆して象牙海岸のAbidjanに到着する物語をつむぎ出すのだ。次の章には b で始まる単語も混ざる。どんな単語が使えるかという外的制約によって物語が規定され、執拗に頭韻を踏む単語の列が、ヨチヨチと物語を生み出していくさまが愉快である。
もう一つ、今度はパフォーマンスが作品としてビデオアート作家ゲーリー・ヒルの「物はなぜゴタマゼになるのか Why Do Things Get in a Muddle?」(1984)に目を向けると、そこではグレゴリー・ベイトソンの同名の「メタローグ」を演じる父親役と娘役が、逆再生したときに英語に聞こえることばを苦労して発音し、それによって確率的にありえない出来事——インスタントコーヒーとグラニュ糖の混合物をかき混ぜるにつれて両者が分離する——が平然と進展する世界を現出させる。
苦行ではあっても、これは楽しい。この世を牛耳る「エントロピーの法則」から這い出そうとするアーティストたちのおバカな身振りは開放的だ。対して『later』はどうだろう。優美さに背を向け、本来自分のものでもない鈍重さにはまり込むばかりではないか。「『遅さ』について」、「『疲労』について」語るテクストも誠実で痛ましい。「みてみて、ほら、面白いでしょ」というメタメッセージが、ここにはない。その代わりに何があるのか。何かポジティブなものがありそうである。
ジョン・ケージや(久保田の主要な研究対象である)クリスチャン・ウォルフの現役時代はこうではなかった。コンセプチュアル・アートの時代、コンセプトはコンセプトだけで十分が強かったのである。アーティストが「思いつき」を競った「前衛の時代」には、まだ「精神=コンセプト」が「身体=パフォーマンス」に指令を出すことが自然なこととして受け止められていたのだ。とはいえ、すでに世界史的なパワーシフトも始まっていたのだ。
20世紀の中葉から顕在化してきた、第三世界の認知、プラック・ミュージックのポピュラー化、エコロジー運動、ポストコロニアルな視座の台頭はみな、大きくみれば一つの出来事であって、その根底には、秩序を固め、いわば楽譜化しようとする精神中枢に対抗して、経験をひらいていこうとする身体の末梢へのアンガージュマンがあるといえる。精神をもって自然を、理性をもって感性を、西欧をもって熱帯を、紳士をもって女子供を、スコア(またはインストラクション)をもってミュージックをコントロールしないこと。出来事を導くコンセプトではなく、生起する出来事にひきずられながら、そのさまを謙虚にドキュメントすること。
『later』の作者は、けっして作者の位置に居座らない。書き放つのではなく、書くと同時に、自らの身体において、理不尽な指示を引き受けて演じる。彼女は、自分自身を、愚鈍な状況へ追いやる作品のコンポーザーであると同時に、自らの仕打ちを受苦するさまを披露するパフォーマーでもある。
繰り返すが、そのパフォーマンスは秘めやかで慎ましい。少なくとも「パフォーマンス・スタディーズ」と題された8つのトラックはどれも、自らの苦境を表だって開示しない。ただし「later」という、アルバムと同名のトラックは違う。ここで演奏者のの受苦が、執拗にリスナーをゆさぶるのだ。そのパッションな声は、鍵盤との幸福な抱合から引き剥がされた指の叫びなのか。理不尽な中枢からの指示に振り回される末梢の発する声は、とまどい、遅延し、かすれ、過剰な息の中にフェイドする。だがそれは消えることなく、なまめかしく箔を反響させ続ける。自分を縛り上げようとすることばを逆に引き込んで、指示と統治のゲーム全体をSM的なプレイの中へ誘いこもうとするかのようだ。
そんなふうに物語が立ち上がる。「パフォーマンス・スタディーズ」の日々の、淡々とした受苦を振り切って立ち上がるそれは、何の物語かは定かでない。闘争とエロスの——とは断定できない。別トラック「メライ-トロイ」は、誰もが知っている「トロイ-メライ」のメロディを、無慈悲な指示に従って組み替えた作品のようではあるが、そこから聞き取れるのは、断片になってしまった無念さではなく、断片が寄り集まって、もうひとつの別なメロディへと自然治癒していく「元気」さである。奏者とその指たちが、ゲームの規則にある程度慣れてきて、オリジナルのすげ替えを、フリーハンドでやってのけているかのように聞こえる。
ここには、ある楽曲を上手に弾き込むのではなく、クリエイティブに「弾き放ち」つつ、もうひとつの別な音楽言語へ翻訳していく、成長の物語が潜んでいる。だとしたら、凡庸さに背を向けたそのアプローチは愚鈍(トロい)どころか、アカルイミライに開かれているように思われる。ソルフェージュのお勉強にはじまる一枚岩的な音楽文化の閉域を内側から食い破り、自由な浮遊を演奏に呼び込むような作品を書くことが可能であることを、久保田翠はこの演奏作品で身をもって示しているのだ。
佐藤良明(さとう・よしあき)
1950年生。アメリカ文化翻訳者。主訳書:グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』、トマス・ピンチョン『重力の虹』、ボブ・ディラン『The Lyrics 1961-2012』。
こども、情景
髙村峰生
11番目のトラックに付された久保田翠のテクストに導かれて、アウグスト・ザンダーの写真集『時代の顔』(Antlitz der Zeit, 1929)のページをめくってみた。これら様々な職業、年齢、性別の人々のほとんどはこちらを向いている。それらは、アンリ・カルティエ=ブレッソンの「決定的瞬間」とは全く違った、個々の人々に内在する<真実>や永遠の相を捉えようとした写真群である。職業が人を作るという信念はドイツ的伝統の一部だ。この写真集に付されたアルフレッド・デーブリンの序文の言葉を引いてみたい。デーブリンは、ザンダーが写真を通じて人々の中に共通する「タイプ」を抽出しようとしていたことに言及しながら次のように言う。
- そのようなタイプの一つは田舎の人々である。これらの人々が安定的であるのは、おそらく、小規模農家の形態が長い間たしかな安定性を持っていたからだろう。このグループはしたがって、その重要性は減じたかもしれないが、消えも無くなりもしなかったのだ。それらの中には、一家族を写した写真もある。そしてたとえ彼らの鋤や農園を見なかったとしても彼らが行っている仕事が過酷で厳しく、単調なものであることが分かるのである。仕事が彼らの顔を堅固で雨風に鍛えられたものにしているのだ。そうした顔は新しい条件においてはいかに変化するか、富や、より軽微な活動によっていかに和らげられるかということも見ることができるのだ。
このような写真の読解は、ザンダーが目指していた「20世紀の人間たち」という大プロジェクトの理念に叶うものであるだろう。ザンダーは社会的階層をもとに人間を7つのグループに分類し、それを約45のポートフォリオに入れていき、いわば社会の実相を写真によって表現することを目指していた。その7つのグループの筆頭に来るのが「農民」であり、デーブリンの評はザンダーの撮った農民が農業を離れているときも農民的であるという、「農民の農民的本質」とでも言うべきものを表現しているとしている。
だが、どうだろうか。「農夫、ヴェスターヴァルト」というキャプションのついた写真集の最初の一枚を見て、これが農夫の顔であると分かる人がどれほどいるだろう。中にベストを着たスーツ姿で、左手は書物をつかみ、右手には眼鏡を持ってイスに腰掛け、白髭をたくわえ、いかめしさのなかにやや寂しげな表情をたたえながらこちらを正視する老人の物静かな様子は、農夫よりは、たとえば、人生に疲労しながらも、知性の炎を燃やし続ける引退したラテン語教授を思わせもする。
典型と差異の戯れ。少しずらすことによって、何がタイプであるとされていたのか、ということが揺さぶられるような経験。ザンダーの試みはナチスによる徹底的な破壊によって、完成されることはなかった。しかし、そもそもこの滑稽なほどに壮大であり、優生学的な危険性を感じさせるところもある試みが、どこまで網羅的であることをめざしたものであったのかは、実のところ、「7つの分類」の残りのカテゴリーを見ることで、疑問に付されることになるだろう。「農夫」のほかのカテゴリーは、「職人・手工業者」、「女性」、「職業と社会的地位」、「芸術家」、「大都市」、「最後の人間たち」である。これがはたして「20世紀の人間たち」を網羅的に分類するのに適切なカテゴリーと言えるだろうか。「職業と社会的地位」などは、いわばカテゴリーに対するメタ的な位置にあるのではないか。「女性」や「大都市」は職業的カテゴリーとは違うのではないか。そして「最後の人間たち」という謎めいたカテゴリーは何か。
こうした分類は、ミシェル・フーコーが『言葉ともの』の序論の最初で言及していたボルヘスの奇妙な分類を思わせるだろう。フーコーは位相の違うカテゴリーが同居する分類を見て哄笑したのだった。ボルヘスの分類は、読者を戸惑わせ、笑わせることを目的の一つとしていただろう。同じことがザンダーに言えるだろうかは分からない。いずれにせよ、真面目であるか不真面目であるかという違いはいささかもザンダーの試みの偉大さを減じない。それはこのライフワークがついに決定的な完結を見ることがなかったとしても、やはり偉大であることに変わりはないことと同じである。我々は、ザンダーの写真を見て笑うことができる。それは、フーコー的な笑いであるとともに、原初の笑い、子どもの頃に我々が笑った種類の笑いであるかもしれない。
バッハやシューマンをしばらく聞いていると、「バッハ的音楽」とか「シューマン的音楽」というのが、楽典などの知識がろくになくてもつかめてくる。音楽はそのような我々の直観に働きかける抽象的本質を持っている。異なるバッハの音楽を聴いても、なにか「バッハ的なもの」という共通項があるということが、言葉で説明できなくても経験的に納得されるのだ。それぞれの作曲家の演奏史はそうした典型的な解釈とそこからのずれの織りなすものであると言えるかもしれない。
久保田翠の<遊び>は、そうした解釈上の「内的差異」に対して、物理的な外的差異を導入する。それは意識の外にある物を意識のうちに挿入する行為だ。優れた演奏家による古典的楽曲の新解釈が聴く者に「新鮮さ」をもたらすとすれば、ここでの経験は全く異なっている。聴く者は解釈以前の状態に引き戻されるのだ。たしかにバッハやシューマンは聞こえてくる。しかし、それはもはや「バッハ的音楽」や「シューマン的音楽」の顔貌を刷新することに貢献するためのものではない。固定されていた歯止めが取れてしまったがゆえの意味の拡散は自由であるとともに不安でもある。建築物は解体され瓦礫が残っている。それを拾いなおしてみるという遊戯は、生産性や効率性などといったこととは、まったく別個の<とりとめのなさ>を持っている。しかし、「トロイメライ」と「メライトロイ」の差異は、「トロイメライ」を正典の地位から引きずり降ろして、その遊戯性を輝かせるだろう。
ザンダーが「20世紀の人間たち」というプロジェクトのために撮った膨大なポートレートの一歩一歩によって、彼が確実に「7つの分類」を完成しつつある実感を持っていたとは到底思えない。むしろ、撮れば撮るほど、農民の農民的本質は何であったのか分からなくなるような逸脱に遭遇し、<とりとめのなさ>を経験したはずだ。しかし、それこそが実験であり人生ではないか。そうだとすれば、最初からふざけたカテゴリーなど設けなければいいと思うかもしれない。しかし、それもまた違うのだろう。最初にカテゴリーを決めて作品をその枠内に沿って制作していくという行為の人工性は、そこからの拡散と逸脱がもたらす喜びをかえって彼に与えてくれるものであったのではないか。
そのような線が、ザンダーと久保田翠を結んでいると思う。
髙村峰生(たかむら・みねお)
1978年生。比較文学、アメリカ文学。関西学院大学国際学部教授。著書に『触れることのモダニティ——ロレンス、スティーグリッツ、ベンヤミン、メルロ=ポンティ』(以文社、2017年)、論文に「燃え上がる枠組、消尽する描写——スティーブン・クレインにおける写真的無意識、近接性、死」『メディアと帝国』(小鳥遊書房、2021年)。
later 光
土方透
●端緒(ゲネシス)
「初め」において出逢うもの、それは「未知のもの」でも、「未見の世界」でもない。そこにあるのは「未知」「未見」以前のもの、「見たことのないということ」そのこと自体が見えない、という情景である。そこにはまだ、なにものかの存在はもとより、非存在なるものも存在していない。存在/非存在という区別すら、そこにはない。だからこそ、そしてそれこそが、「初め」なのである。
「初め」は、二項を拓く。神は初めに、「光あれ」と発した。そこを基点に、光/闇が分けられた。この二項は、有/無、可能態/現実態、同一性/差異性という二分の両翼へと拡がりゆく。禁断の木の実を食したことで無辜と罪過が分けられ、永遠の生を与えられていた命には、楽園からの追放により死がもたらされる。
●棄却(アウフヘーベン)
モーツァルトのアヴェ・ヴェルム・コルプス (Ave verum corpus)が放つ初めの音、それは闇に一つの光が生まれ出たその音だった。この世に人の子として生まれし神の子が、十字架上の受難と臨終の試練という一連を告げる、その始まりの音である。
めでたし まことの御身体よ 乙女マリアより生まれ給もう
Ave verum corpus natum de Maria Virgine.
それは待ち焦がれていた救世主が、遂にこの世に降誕したその瞬間だった。それを基点に世界は、以前(Before Christ)/以降 (Anno Domini)に分けられた。
人々のため犠牲となりて 十字架上でまことの苦しみを受け
Vere passum immolatum in cruce pro homine
貫かれたその脇腹から 血と水を流し給いし方よ
cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine.
我らの臨終の試練を あらかじめ知らせ給え
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
イエスはこの世において、生を否定され、十字架上で死をもたらされた。そして、復活を遂げた。復活は、生/死という対置を棄却(アウフヘーベン)する。もはやここに、「(始まりとしての)生/(終わりとしての)死」という二分はない。降誕は、この棄却のための基点であった。だからこそ降誕という出来事は、すべてを照らす「光」なのだ。光に照らされた闇に、漆黒を見ることはない。光が見せてくれるのは、それが見えないということである。
●彷徨(さまよい)
Laterが鍵盤(ハンマー)を落とす。其の場所(トポス)から、音と静寂の共奏が世界を拓く。その「初め」に与った己は、見えないということすら見ることのないこの世界に放たれ、彷徨い始める。
その姿はあたかも、初めて這う赤子のようである。赤子は、自らの伸ばす四肢と地面との距離を知らない。地面がどのような感触のものか、そもそも四肢を降ろしたとき、そこに何か「感触」というものがあるのか、それすらも知らない。あるいは、暗闇の海に船を出す船頭、星一つなき夜に旅立つ飛行士のそれかもしれない。船頭は、見えないものに目を遣りながら漆黒の中を漕ぎ、飛行士は、確かめられないということを確かめながら暗闇の中を飛ぶ。己は、途を自らの手で書き足しながら、その途を進み行く。
●闇に打つ槌(ハンマー) あるいは Le marteau sans maître,
神は上位から、あるいは外側に座して、この世界を創造した。己は、世界の内で、周りに張り回られされているであろう壁に手を這わせ、世界を推し量らんとする。手の微かな重みに綻ぶ襞を探り、それにもたれかかろうとするが、音と静寂が耳許で、「そこではない」と囁く。
己は引き戻され、再び彷徨いはじめる。綻びを繕うかのように手をまさぐらせながら、戻され/進み、進み/戻されていく。己は、「初め」に与ったという原的な所与性に包まれて、毀損/修復を続ける。槌(ハンマー)に主(あるじ)はいない。槌(ハンマー)が主(あるじ)なのだ。
●離脱と回帰
作品は、その始まりとともに終わりを暗喩する。作品に初めて触れる者は、いずれ訪れる突然の終わりに身構える。音が止み、静寂の後に次の音が来ないとしても、終わりを確信することはできない。ただ決疑的に宣言するという仕方で、つまり自身に暴力的に告げるという仕方で、作品の拓いた世界が閉じられたことを己に言い聞かせるのである。世界から締め出された己は、余韻をまさぐり、記憶のシナプスを辿ろうとするが、得られる心像は、もはやその世界のそれではない。
こうして己は、作品の拓く世界にもう一度歩み入ることを選ぶ。もはや再訪者は、あの「初め」以降、この世界には始まりと終わりがないこと、この世界で起こる一切が「一つのこと(Einheit)」であることを識っている。
●later
laterは、見えないというかたちで、そしてその都度そっと、今‐此処を拓くこの場所(トポス)を差し出す。
そこで、人は問うかもしれない。
「ゴドーは来るのか?」
「今は わからない
今は彷徨い また戻って問えばよい later!」(イザヤ21:11)
なおも、人は問うだろう。
「光はどこに?」
「光は闇に輝く この曲の後で later!」 (ヨハネ1:5)
===================================================
コロナ禍の2020年、待降節(アドベント)第4週に
土方 透(ひじかた・とおる)
1956年生。理論社会学。聖学院大学政治経済学部教授。
Das positives Recht als soziales Phänomen (Duncker & Humblot)、Riskante Strategien (Hrsg. Westdetscher Verlag.)『法という現象』、『世界社会の宗教的コミュニケーション』(編著)など。
Sans adjectif(形容詞なしに)──久保田翠『later』によせて
星野太
昨年まで勤めていた美術大学で、毎年「美学」という授業を受け持っていた。毎回ひとつずつ、「模倣」「表現」「創造」といった、制作者にとっては馴染みの語彙に批判を加え、その明証性に疑問を投げかけていく──そうした内容の講義だった。美術科の必修授業だったので、興味のほどはともかく、毎回100名ほどの学生が教室に集っていた。
その授業では、「即興」の回でグレン・グールドのゴルトベルク変奏曲を流すのを習わしとしていた。即興とは何か、ということについて一通りの説明をしたのちに、演奏という行為がある意味ではすべて即興にほかならない、ということを感じてもらうためだった。つまり、そこでわたしが学生に聞かせたかったのは実はピアノではなく、構築性を旨とするスタジオ録音に悠然と場を占める、このピアニストの鼻唄であったのだ。
そして今年度、やむをえない事情が重なり、離職したはずの大学の「美学」をもう一年だけ担当することになった。大方に漏れず、すべてオンラインでの授業であった。いつも教室のスピーカーから流していた大音量のグールドも、わたしのラップトップの貧弱な内蔵マイクからZoomで送らざるをえない。そのような酷薄な環境で、このピアニストのかすかな鼻唄を聞き取れた者は誰一人としていなかったにちがいない。
この数ヶ月、自宅でひとり過ごす時間があると、いつも久保田翠の『later』を流していた。音楽を流しているというより、ただそこにいてくれるような録音だと思った。日を追うごとにその思いは強くなった。その違和感のない佇まいの理由が長らくわからなかったのだが、先日PC越しに流したグールドの演奏──あるいは鼻唄──を聞きながら、何かがすとんと腑に落ちる心持ちがした。
録音されたもののなかには、いかなる方法によっても取り返しのつかなくなってしまった過去が記録されている。どのような過去であれ、それを取り戻すことは原理的に不可能である以上、それはあまりにも当然のことだと思われるかもしれない。しかしそれでも、そこに記録されたものが、もはや取り返しようのないものだと感じさせてくれる録音は、すくなくともわたしにとってさほど多くない。
そして、ここに録音された過去は、まさしくそのようなものだった。
音楽が享楽の対象であるとき、そこに同様の切実さが宿ることはほとんどない。その意味で、この録音は音楽ではないとすら思った。ロラン・バルトが言うには、形容詞は映像、あるいは支配と死の領域に属するという(『彼自身によるロラン・バルト』)。わたしもそう思う。おそらく音楽についても、事情はさほど異なるものではない。わたしはこの録音に形容詞を与えたくはない。それは、やはりバルトが言うように、友人を形容詞によって語ることがないのと同じことである。
星野太(ほしの・ふとし)
1983年生。美学、表象文化論。早稲田大学社会科学総合学術院専任講師。著書に『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)、『ことばを紡ぐための哲学』(共著、白水社、2019年)、訳書にリオタール『崇高の分析論』(法政大学出版局、2020年)、メイヤスー『有限性の後で』(共訳、人文書院、2016年)など。
音に遅れる
細馬宏通
Performance studies1-6には、パフォーマーのためのインストラクションが記されている。たとえば1には、こんな風に。
- 任意の楽譜を選びなさい。
- 骰子をふり、1~5までの数字をひとつひとつの音に書き込みなさい。
- その数字を指番号として演奏しなさい。
これは、ピアニストのための指示だけれど、きき手であるわたしは、きく方法としてのインストラクションとして受け取る。音をききながら、骰子によって偶然に割り振られたであろう、親指、人差し指、中指、薬指、小指が、それぞれもつれるように、次の音へと移っていくのをイメージしている。ときにはとんでもない交差や跳躍によって、キーを弾いているであろう指の運動を、ペダルで引き延ばされた時間の中で想像する。
けれど一方で、わたしはインストラクションによって、ただ視覚的な指の運動を明らかにしようとするのではない。きき手であるわたしには、1~5までの数字は伏せられている。二つの音が鳴り、それらの音がダンパー・ペダルによって名残っている間に、その名残りの中から抜け出てきたように一つの音が鳴る。わたしは、数字を伏せられたまま、その抜け出てきた音と、直前の響きとのあいだに、連続したメロディをききとる。そういう自分のメロディ認知を、骰子によって双六のコマを一つずつ進めるように、たどっている。音がまずあって、音から音へと運動する身体があとからやってくる。
久保田翠のインストラクションを読むとき、わたしは密かに「想像せよ imagine」という命令を読み取っている。想像してごらん。指がもつれてるということを。想像してごらん。一つの声部がずらされていることを。唐突に終わる曲の終わりは、決然と始まる曲の始まりかもしれないことを。そして想像する、いままさに音を生み出しつつある身体のことを。しかし、まだ身体は形にならない。息が容易にはことばの形にならないように。身体は音に遅れる。
細馬宏通(ほそま・ひろみち)
1960年生。人間行動学。早稲田大学文学学術院教授。編著書に、『うたのしくみ 増補完全版』(ぴあ)、『いだてん噺』、『ELAN入門』(ひつじ書房)、『二つの「この世界の片隅に」』『絵はがきの時代』『浅草十二階』(青土社)、『介護するからだ』(医学書院)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くか』(新潮選書)など。
打鍵のためのレッスン
山田亮太
Instruction:
任意の音楽を選びなさい。
それを聴きながら詩を書きなさい。
その音楽は人間の手で演奏されたものであることが好ましい。
音楽を構成するひとつひとつの音が人間の動作とひもづいているとよい。
詩を書くための道具は、音楽の演奏に用いられる楽器と似た機構を持つと好ましい。
音楽を聴き終わるのと同時に詩を書きあげること。
Note:
『later』収録の「Merei-träu メライトロイ」を聴きながら、詩を書いた。
ピアノの音が一音鳴るたびに、パソコンのキーボードを一度だけ叩いてよいという原則にのっとって書いた。
ピアノの鍵盤が叩かれるタイミングとキーボードを叩くタイミングができるだけ一致するように努めたが、正確ではない。
また、そもそもピアノは複数の音を同時に鳴らせるのに対して、キーボードは原理的にひとつずつしか叩けない。
したがってどれほどこの作詩法に習熟しようとも、キーボードの打鍵のいくつかは音楽から遅れざるを得ない。
以下は、100回の試行の中から抜粋したもの。
004
なぜあなたはそんな風に言うのか
わかっているはずなのに
早く終わってしまえばいいと
残り少ない今日を最後まで楽しもうとして
ねむるのを我慢しているのか
開いた眼を見てほら
必ず起きてしまうだろう
010
さては見えない猫を飼っているのだな
壁の向こうでおじいさんが苦しそうな声をあげて
腕を大きく振ってそこにいるのだと
必死にアピールをしている
見てみぬふりをして立ち去ろうと急ぐも
つまずいてころんでしまう
世界はひろい
016
なんでもよいからほしいものを家
ひょっとすると世間でさわがれている
あまりにもさびしいのでごまかして
間にあっていると言い訳をしてたぶん
さえぎるように夜を
じっと待っている犬の目をして
017
残り物の服を着飾ってかえる
けれど船に打ち付けたしるしを
手でなぞるようにはねて
水を飲む口がそばから
風邪をひいたのか別の何かなのか
わからない怖さをうち消すために
019
くるまれた朝に
祈りを雑に終わらせては
残り物の昨日を盾に
あるくときの歩幅で走っている
その姿を写真におさめて
大切なものであるかのように
人に見せる
022
明るい嘘をついた
できれば信じてしまいたいという思いで
言葉はいつであれ意味を帯びてしまうから
帰らない方がいいとしても
激しく否定してもつかんでも
早くそのままでいられるように
026
言い訳がましいので黙っていたが
そんな指令は出ていなかった
ただ残りの時間をできるだけ静かに
やり過ごすことだけが
与えられた任務だったのだ
それなのに大きな手で
行き先は
028
たりない部分はそう
そうだよとあなたはいって
隠すように手を
手をかざして
ふたりまでが限界だったから
いのちや健康のことを
できるだけ考えないようにして
いちばんさいしょに来たバスに乗る
037
変わり者の海に呼ばれている
あらあらと炎の燃え盛る
くるしみの別の名をつけて
ひどい仕打ちを記録するには
この脳は容量が足りなすぎるから
頭を割ってもう一度
はじめから
041
こどもの冬の偽物の扉
けれどたしかにつながったこぶと
ひっくりかしの額に
やかれにいくそんな重なった矢先に
再会のそぶりをはやめて
針金のここちを背景に
045
融通のきかない声利する
二重の本に擬して狂う
外語区の林とふいの氾濫へ
わかりを住みてきて版
やいでふくうはりして
実感に代わり映えしふるこくと
へみすくう不和に
047
たぬせば敗とほらえわる
じゃこぶに奏でうつすべつにおれ
空刺してファラオ
こりからんでおすてこの
生肉のそこないすくう
節度をほえはらまれて
肺となす
051
でろでろでにしたる
ひてれしてばこだに
はりおぺてくるげそ
ひじしぐつねそにひと
じしれくるかえ
ふるへともにへでれしたら
はねのふりけんませよ
ひちひすれそん
に
056
なあとけどもふるわれて
ひにちふたすふぁかれすを
れっぱにらんどるとも
ふさぎけれずは
へたに恋するはふてをじして
にきしたをはい伴なわず
絶食のくつわぬしへばれば
こんていにいおわす
058
湖には足をつけて涙する権利を与えず
働くことの呼び覚ましとおしまいに
人生の墓場に可能な元気を
湧けて沸騰する幻日にこらえきれず
ぼそぼそと砂を噛むくらいに
059
ゆうべ意識をとりもどしたはずが
いちじかんでまたもとにかえってしまった
はずがないと思いこんでいたはずがないと
ないと思う思うくらいなら
わけもなくかなしいとかなしいと
暮らすくらす限界を超えて得て
ひみつを全部教えて共同で
062
根と猫と遠い日の再び救う
狭いテーブルにいっぱいの食べ物と
ノートに書きつけたぐねぐねの
楽器にはまだ手にした時の記憶が
がんばってよい日にする
平和な
063
楽をして二階から降りてくる方法を
たずねて無理をして呼ばれてもいない
はじめからおしまいまでの一時間を
二度とやってこない人を待つ心持ちで
やめてくれとあなたは言うのか
平穏な
067
かがんでみたのは別荘の
くらいよ道にかじかんだ手で
頬をさすった瞬間に
遅れてきたひとの名前をみんなの前で告げて
晴れやかな笑顔であいさつをした
昨日もそうやってやり過ごしたことも
忘れて忘れようとして
068
財宝を見つけたので一目散に
走って逃げた放火後の楽しい気分を
忘れないように紙に書いておく
それを見らればかにされ
ひとのおこないを裁くのはなんてむずかしいのだろう
残りの時間をすべて使って怒る
069
すらりと伸びたからだを折り畳んで
うしろの壁につるしておく
元気の失ったいきものたちを順に並べて
いっぱつずつ殴るように
何が間違っていて正しかったのかを
よく考える午後
弁当箱にはひとの
073
ばえみしらるきふと
ふてねすとる
はなせぱもぞそらせすなぐてさおれす
ばらせよほらませみご
たつもとみせるしふぁまみ
ふぉらすとせれむすと
085
おろおろとゆうべバカンスにでかけ
ひとに言えないことをしたはずなのに
少しも悔いはなく今日を最後まで
私のものとしてはるか遠い
山の向うを指さして
さめざめと宣告をするのだろう
086
悪いおこないを告白するにはうってつけの場所だ
払い戻すにはせっかくの希望をあきらめて
変な格好でいちばん前に座って笑顔で
みんなの注目をいっしんに集めていると
089
逃げてきてよいとことわっておいたから
頭のなかではわかっているはずだろうし
からだもたぶんついてくる
歯車が狂っていて最高にうまくいく
ずいぶんとワニのきもちがわかってきた
ねえそれでどうしたというのか
手を洗え
090
死んでしまったので裏庭に穴をほって埋めた
アイスの棒をたてて手を合わせて願った
もしも生き返ってもう一度ここに来るときは
前よりも強く大きくなって
決して死なない者になれ
それができないならずっと土のなかにいろよ
092
遠くへ行く出来るだけ遠くへ
少しのお金とペットボトルを持って
帽子にはいっぱいの虫が入っていて
それを道端に捨てて歩いてきた道のりを
きみにわかるようにして
遠くへ行くできるだけできれば
095
わからないのなら黙っていて
過ぎたことは考えずに
なんの意味があるのかは未来のひとが決める
とても安心できる
素直にふりあげた手をおろして
まえだけを見ていまは
098
地球にはたくさんの生き物がいて
全部の名前を覚えてはいない
石に書いておくには多すぎるから
手を叩いてなかったことにする
がんばればなんだってできるが
がんばりたくはない日もあるし
たいていはそういう日だ
山田亮太(やまだ・りょうた)
1982年生。詩人。TOLTAメンバー。詩集に『ジャイアントフィールド』『オバマ・グーグル』(小熊秀雄賞)。